銀行のあとに、もう一つの現実を突きつけられた
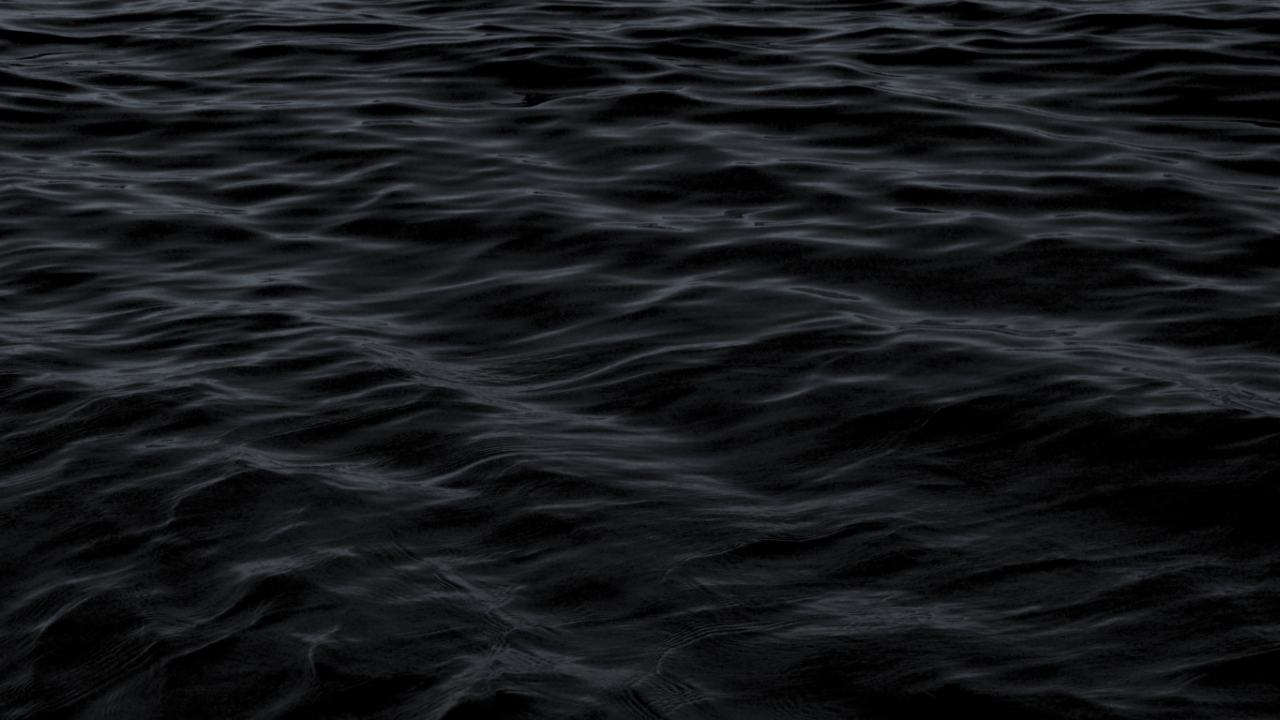
銀行のあとに
銀行へ行ってから、それほど時間が経っていない頃だった。
妻の母から、「一度会って話がしたい」と連絡があった。
その頃の私は、銀行で起きた出来事をどう受け止めればいいのか、まだ整理がつかないままでいた。
理解したつもりになろうとしては、どこかで立ち止まる。
考えようとすると、頭の奥が重くなる。
そんな状態だった。
義母と会えば、銀行の話に触れることになるかもしれない。
そうなったとき、何を話せばいいのか。
どこまで踏み込んでいいのだろう。
考えれば考えるほど、気持ちは混乱していった。
それでも、避けては通れない話があることは分かっていた。
これからの生活のこと。
子どもたちの将来のこと。
妻が亡くなったあとに残された、私たちのこと。
義母が話したいのは、きっとそういう内容だろう。
私はそう自分に言い聞かせて、その場に向かった。
少なくとも、まったく違う角度から言葉が投げかけられるとは、想像していなかった。
予想外な言葉
義母が最初に口にしたのは、子どもたちの話でも、今後の生活の心配でもなかった。
迷いのない、「お金の話」だった。
「あなたたちの家計は、ずっと火の車だった」
その言葉を聞いた瞬間、頭の中で何かが止まった。
意味が分からなかったわけではない。
ただ、その言葉を、自分の現実として受け取る準備ができていなかった。
義母は、メモ帳のようなものを取り出し、そこに書かれた数字を私に見せた。
説明は、ほとんどなかった。
並んでいるのは、ただの金額だけだった。
それは、これまで妻に貸してきたお金の合計だという。
数字を見たとき、まず浮かんだのは、驚きではなく戸惑いだった。
私は、その場で言葉を失った。
頭の中で、これまでの生活を必死に振り返っていた。
余裕のある暮らしではなかった。
それは確かだ。
だが、生活が破綻するほど追い詰められていた記憶はない。
給料があり、住宅ローンを抱えながらも、別の住宅からの家賃収入もあった。
特別な贅沢をしていた覚えもない。
外食を重ねていたわけでも、高価な買い物を続けていたわけでもない。
日々の暮らしは、慎ましいとは言わないまでも、身の丈を大きく外れてはいなかったはずだ。
それなのに、銀行の残高はほとんど残っていなかった。
積立金も、きれいにゼロになっていた。
さらに、その裏で、親からお金を借りていたという話まで出てくる。
それらの事実を並べてみても、私の中では一つの線として結びつかなかった。
どこかで、計算が合わない。
そう思えば思うほど、私が見ていた「日常」そのものが、何だったのか分からなくなっていった。
胸に浮かんだ疑念
義母は、銀行で起きた出来事を知っているのではないか。
何か具体的な根拠があったわけではない。
証拠と呼べるものも、何ひとつなかった。
ただ、その場で話を聞いているうちに、ふと、そういう考えが浮かんだ。
理由を探すより先に、感覚として立ち上がってきた、というほうが近い。
自分でも意外なほど自然に、その可能性が頭に浮かんでいた。
当初、私は銀行で起きたことを、きちんと説明するつもりでいた。
積立金が消えていたこと。
不審な手続きが行われていた可能性があること。
隠す理由はない。
そう思っていた。
だが、話の流れが変わった瞬間、その考えは揺らいだ。
すべてを話していいのか。
話してしまっていいのか。
その感覚が、私を強くためらわせた。
私は、銀行で積立金に不審な点があったことだけを伝えた。
誰が関わっていたのか。
どこまで分かっているのか。
その核心には触れなかった。
代わりに、第三者が関与している可能性があること。
警察に相談することも考えていること。
あえて、少し強い言葉を選んだ。
本気で決意していたわけではない。
ただ、相手の反応を見たかった。
そう言ったほうが正確だった。
義母の表情が、わずかに強張ったように見えた。
それが動揺だったのか、戸惑いだったのか。
あるいは、私の見間違いだったのか。
判断はできなかった。
ただ、その一瞬の沈黙が、重く胸に残った。
残り続けた感情
義母が示した金額について、私ははっきりと伝えた。
そのお金は、返せない、と。
身に覚えがなかった。
お金を借りるほど困っていたという実感もなかった。
突然突きつけられた話を、そのまま受け入れられる状態ではなかった。
義母は、それ以上踏み込んでくることはなかった。
話は、そこで終わった。
だが、私の中では、何ひとつ終わっていなかった。
家計は本当に火の車だったのか。
義母の話は、どこまでが事実なのか。
銀行で起きた出来事と、この話は、どこかでつながっているのではないか。
そして何より、自分の知らないところで、何が行われていたのか。
怒りだけなら、まだ向き合えたかもしれない。
悲しみだけなら、時間に任せることもできただろう。
だが、胸に残ったのは、信じていたはずの関係が揺らいでいく感覚だった。
妻は、何を私に見せず、何を共有しないまま過ごしてきたのだろう。
私が信じていた家族とは、何だったのか。
それは、いつから、どこで、静かに崩れ始めていたのか。
答えは見つからないまま
これから先に、何が明らかになってしまうのかという不安だけが、
確実に、私の中に積み重なっていった。





