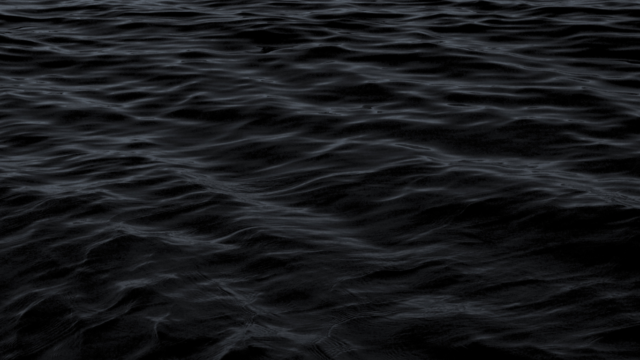疑念だけが残った

答えが出ない時間
妻を亡くしたあと、残された人が最初に向き合うのは、悲しみだけではない。
葬儀の段取り、役所での手続き、家の片づけ、そして避けては通れないお金の問題。
気持ちの整理がつかないまま、現実だけが淡々と目の前に並べられていく。
この記録は、妻を亡くした私が、遺留品や書類の整理を進める中で、そこで初めて知った現実について綴ったものだ。
家計の中身、数字の積み重なり、そして「やはりそうだったのか」と思わざるを得なかった事実。
生前、私は家のお金に深く関わってこなかった。
以前の記事にも書いたように、通帳を見ることができなかったからだ。
通帳の話を切り出すと、決まって揉めた。怒鳴り合いになるわけではない。
だが、話は噛み合わず、最後には空気だけが重く残る。
その繰り返しが、「この話題には触れないほうがいい」という感覚を、私の中に作っていった。
「ちゃんとしているから」
妻は、そう言った。私はその言葉を信じたかった。
だが正直に言えば、疑問が消えたことは一度もなかった。
信じ切れていたわけではない。どこかで、常に違和感を持ち続けていた。
数字の話を避ける態度。
細かい説明を嫌がる様子。
はっきりしない返事。
小さな引っかかりは、何度もあった。
それでも私は、深く追及しなかった。
知らなかったのではない。疑問がなかったわけでもない。
喧嘩をしたくなかったのだ。
感情がぶつかり合い、関係が壊れるようなことだけは避けたかった。
そうやって私は、違和感に蓋をしながら、日常を回していた。
見ないふりをすることで、家庭は保たれていると思い込んでいたのかもしれない。
だが、妻が亡くなったあと、現実は静かに姿を現し始めた。
住宅ローンの滞納。督促状。延滞金の通知。
医療費の領収書や、見覚えのない支払いの記録。
一つひとつは、特別なものではない。
だが、それらが並んだとき、胸の奥に冷たいものが広がっていくのを感じた。
驚きよりも先に浮かんだのは、「やはり、そうだったか」という思いだった。
私は、気づいていなかったのではない。
ずっと、どこかで分かっていたのだと思う。
ただ、その先に進む勇気がなかった。
これは、特別な家庭の話ではない。
どこにでもある、ごく普通の家族の中で起きていたことだと思っている。
だからこの記事は、誰かを責めるためのものではない。
明確な答えを示すつもりもない。
ただ、違和感や疑問を抱えたまま、それでも目を逸らし続けてしまった一人の記録として、残しておきたいと思った。
答えが出ない時間の中で立ち尽くしていた、その感覚も含めて。
沈黙が示した違和感
義母と電話で話をして以来、連絡は一切なかった。
それは、どこか予想していた展開でもあった。
感情的なやり取りのあとに残る沈黙は、時に答えそのものになる。
冷静になって振り返ると、不自然な点はいくつもあった。
娘が亡くなった直後だというのに、義母が切り出してきたのは「お金の話」だった。
悲しみを共有するでもなく、今後の生活を案じるでもなく、具体的な金額の話だけが先に出てきた。
妻の父は、妻が亡くなる数年前に病気で亡くなっている。
その際、入退院を繰り返していた時期の医療費の領収書が、なぜか我が家に残されていた。
だが、病院の医療費をきちんと支払っていた形跡は見当たらなかった。
それにもかかわらず、「娘にお金を貸していた」と言われても、正直、腑に落ちなかった。
妻の両親は団地住まいで、生活に余裕があるようには見えなかった。
住宅ローンや家計の実情を思えば、娘に貸せるほどの資金が本当にあったのか。
疑問は消えなかった。
不自然さが積み重なっていく
おかしい。
そう感じる場面は、一度や二度ではなかった。
さらに思い返すと、妻が亡くなる少し前、義母は新車を購入していた。
ところが、妻が亡くなった直後、その車は別の車に変わっていた。
私の給与からの資金の流れが止まり、維持できなくなったのではないか。
すべては私の推測に過ぎない。
それでも、このことを考えるたび、胸の奥に重たい感情が残った。
以前の記事でも触れたが、当時の私にとって、自分の車にガソリンを入れることすら簡単なことではなかった。
車はサビも多く、10年以上乗り続け、走行距離は20万キロを超えていた。
買い替えについて相談したこともあったが、返ってきたのは
「まだまだ乗れるから大丈夫」
その一言だけだった。私が我慢を強いられていたその裏で、義母は新車を購入していた。
確かなことは、何一つわからない。
誰のお金で買われたのか、どこからその余裕が生まれたのか、証拠になるものは何もない。
それでも、心の奥に残るものがある。
「もしかして、私のお金が使われていたのではないか」
そう考えてしまう自分を、責めきれない現実がそこにはあった。
断定はできない。
それでも、何かがおかしいと感じるだけの材料は、十分すぎるほど揃っていた。
確証がないからこそ、疑念だけが残り、今も心の中で静かに溜まり続けている。
違和感の正体
義母が、妻の死後間もない時期に私を呼び出し、お金の話をした理由も、今では理解できる気がする。
すべてが明らかになる前に、少しでも現金を確保しておきたかったのではないか。
そう考えると、あの場で感じた違和感の正体が、少しずつ形を持ち始めた。
現実の壁と、「もう追わない」という選択
その時の私は、妻、義母、そして妻の弟が何をしていたのかを、はっきりさせたいと考えていた。
警察や弁護士にも相談し、これまでの経緯や、手元に残る書類について説明した。
だが、返ってきたのは極めて現実的な答えだった。
「できるのは、事実確認と注意、警告などを口頭でする程度でしょう」
それ以上の対応は難しい。
そう告げられたとき、現実の壁の厚さを痛感した。
手元には、住宅ローンの滞納、督促状、延滞金の記録など、多くの資料が残っていた。
それでも、すべてを白黒つけることは簡単ではなかった。
怒りはある。違和感もある。
それでも、どこにも進めなかった。
私は、止まっていた。
いちばん苦しかった時間
夜になると考えすぎて眠れず、朝になれば、何も変わらない現実がまた始まる。
判断もできず、結論も出せない。
ただ、時間だけが過ぎていった。
今振り返ると、この「答えが出ない時間」こそが、いちばん苦しかったのかもしれない。
納得できたわけではない。
だが、この一連の出来事を通して、はっきりと分かったことがある。
家計やお金の問題は、知らないままでいられるものではないということ。
そして、一度現実を知ってしまえば、もう避けて通ること出来ないということだった。